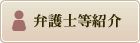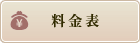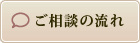準抗告で身柄を解放するには?【弁護士が事例で解説】

| 罪名 | 傷害罪(刑法204条)・器物損壊罪(刑法261条) |
|---|---|
| 解決までの期間 | 2ヶ月 |
| 弁護活動の結果 | 勾留に対する準抗告認容、示談成立により不起訴 |
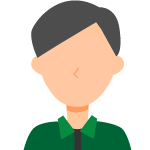
Sさん(40代男性)
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
酒に酔ってトラブルを起こしてしまったSさん
Sさんは仕事帰りに飲みに出て、泥酔した状態で繁華街を歩いていました。
しばらく歩いたところで、通行中の車とトラブルになり、車から降りてきた相手を殴って怪我をさせた上に、相手の車を殴って一部を破損させてしまいました。
Sさんは事件の後、任意で取り調べを受けたものの、被害者の傷害結果がそれなりに重いものであったことやSさんの事件当時の記憶が曖昧であることなどから、後日逮捕・勾留をされてしまいました。
勾留に対する準抗告が認められ、釈放
Sさんは、記憶は曖昧ながらも、怪我をさせたり車を壊したりしたこと自体は間違いなく覚えており、被害者との示談交渉を私たちに依頼されました。
しかしながら、Sさんには貯蓄がほとんどなく、被害者への示談金を支払うためにはどこかから借り入れを行わなければなりませんでした。
借り入れを行うためには、当然Sさんが自ら担当者と話す必要がありますので、事件解決のためには一刻も早くSさんの身体拘束を解く必要があると考えました。
そこで、私たちは直ちに勾留に対する準抗告を行い、被害者との示談のためにもSさんの身体拘束を解くことが必要であることを強く訴えました。
その結果、裁判所は勾留の要件を満たしていないと判断し、勾留に対する準抗告が認められました。
相手方の示談金も適正額でおさめ、不起訴処分を獲得
その後Sさんは無事に借り入れを行うことができましたが、被害者は著しく高額な示談金を求めていました。
車を壊され、怪我をさせられたことに対して怒る気持ちは理解できますが、相手は単純にこの機会を利用して大金を得ようと考えているようでした。
そのため、私たちは適正な金額を算定した上で、それ以上の示談金は一切支払わないという毅然とした対応をしました。
交渉は難航しましたが、最後は被害者にも納得してもらうことができ、適正な額の示談金を支払う代わりに、刑事処罰を一切求めないという内容で合意ができました。
Sさんの反省が検察官に伝わったこともあり、合意書を証拠として検察官に提出してから間も無く、Sさんは無事不起訴処分となりました。
今回のポイント
勾留とは

勾留とは、被疑者ないし被告人の身柄を拘束する手続です。
勾留は、被疑者の身体の自由を奪う手続です。
簡単にできるとなると、人権侵害にもつながるため、法律に定められた要件を満たすことが必要となります。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです(刑訴法207条1項、同60条1項)。
- ① 被疑者が定まった住居を有しないとき。
- ② 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- ③ 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
準抗告とは
準抗告とは、容疑者や弁護人の請求により、裁判官が出した勾留決定を破棄するよう求める手続きをいいます。
勾留決定が不当であると認めてもらうために、上記の勾留の要件を満たしていないことを説得的に訴える必要がります。
勾留が認められる確率はとても高いと言われています。
2018年では、9万9967人の勾留請求がされ、その約95%が認められています。

参考:2019年弁護士白書
準抗告の根拠
勾留に対する準抗告についての根拠条文は刑事訴訟法第429条1項2号となっています。
準抗告の制度は、迅速・簡易な解決のために認められている制度です。
そのため、対象となる命令や処分は、迅速な解決が求められるものだけが限定的に定められています。
<刑事訴訟法第429条1項>
一 忌避の申し立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受けるものに対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口
準抗告の要件
準抗告は、刑事訴訟法第429条1項各号に定めてある裁判に対してであれば行うことが出来ます。
裁判に対する異議申し立ての手続きですので、勾留の裁判に対する準抗告が認められるのは、勾留の要件を満たしていないと裁判官に判断してもらえたときということになります。
勾留の要件は、
- ① 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- ② −1定まった住居を有しないこと
- ② −2罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
- ② −3逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
- ③ 勾留の必要性があること
です。
準抗告では、これらの要件のうち、いずれかを満たしていないことを主張します。
準抗告が認められるほとんどのケースでは③勾留の必要性がないと判断されているように感じます。
準抗告と特別抗告の違い
特別抗告とは、刑事訴訟法によって不服を申し立てることが出来ない決定・命令に対して、上告理由となりうる事情がある場合に限って異議申し立てが出来ることとされている手続きです。
上告理由は憲法違反や判例違反といったもののみですから、極めて限定的であるほか、申し立ての対象も最高裁判所となり、特別抗告が出せる期間も決定・命令等が出されてから5日間と限定されています。
準抗告やそのほかの手段では異議を申し立てられない場合に行うのが特別抗告ですから、勾留に対しての特別抗告は出来ません。
準抗告と保釈の違い

準抗告と保釈は、どちらも勾留されている状態から身体拘束を解放するという意味では共通しています。
しかしながら、準抗告は勾留の要件が満たされていないことを理由に勾留の効力を争う異議申し立ての手続きであるのに対し、保釈は、勾留の要件が満たされていることを前提に、裁判が終わるまでの間、身体拘束の解放を求めることが出来る制度です。
また、保釈は起訴された後に初めて認められている制度ですが、勾留に対する準抗告は勾留決定が出た後直ちに行うことが出来ます。
両者にはこのような違いがあり、その場面ごとに適切な方法で身体拘束の解放を求めていく必要があります。
勾留延長に対する準抗告
検察官の請求によって、最大10日間、勾留の期間が延長されることがあります。
この場合も、勾留に関する裁判であることに変わりはありませんので、勾留に対する準抗告と同じ根拠条文に基づき、準抗告を行うことが可能です。
ただし、勾留延長の要件は勾留の要件とは異なりますので、勾留延長に対する準抗告を行う場合に主張すべき事由も異なることになります。
具体的には、勾留延長が認められるべき「やむを得ない事由」の判断要素である
- ① 捜査を延長しなければ検察官が事件の処分を判断できないこと
- ② 10日間の勾留期間では必要な捜査を終了することが出来ないこと
- ③ 勾留の延長により捜査の障害を乗り越えられる見込みがあることのいずれかが認められないこと
を主張することになります。
また、勾留延長に対する準抗告を行なった場合、延長を全く認めないという結果を導くこともありますが、延長期間を10日から5日に減らすというような判断を裁判官がすることもあります。
0か100かという判断ではないことも勾留に対する準抗告の場合と異なります。
準抗告が認められる確率
2018年の準抗告申立件数は1万3263件であったところ、認容されたのは約19%にとどまっています。

参考:2019年弁護士白書
したがって、一般的に勾留の準抗告認容率は決して高いものとはいえません。
まとめ
上記の事例では、事案に即して重要な点に絞って裁判所を説得したことが功を奏した形になりました。
また、被害者といえども、法外な金額を要求する相手には毅然とした対応を行うことが重要となります。
傷害事件で警察から捜査を受けている方、ご家族が傷害事件を起こしてしまいお困りの方は、刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所に、まずはお気軽にお越しください。